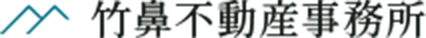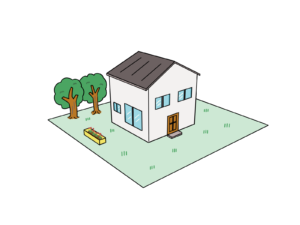現在所有しているアパートの経営を続けるか、売却するべきか悩んでいませんか?
アパートを売却する場合は、個人の戸建売却に比べて高額な取引となりやすく、さらに入居者がいるため専門的な知識が必要です。特に初めて売却する場合は、知らずに損をしてしまったり買主や入居者とのトラブルに発展したりするケースもあります。
ここでは、アパートの売却を検討している方へ向けて、売却を判断するポイントやコツ、失敗しないための売却時の流れについて解説します。
売却したいアパートの取得は相続?購入?
「アパートを売却するべきかどうか」迷ったときにまず確認したいのが、対象となるアパートを取得した方法です。
なぜなら「相続したアパート」と「購入したアパート」では、同じ売却でも最終的な損益に差が出るためです。
例えば、相続したアパートは取得時に高額な初期投資をしておらず、売却を行ったとしても損失が出にくいため、売却のハードルは低くなります。
一方、「購入したアパート」でローンの残債がある場合、売却額でローンの完済ができるか、もしくはできなかった際に一括返済できる資金はあるのかなど、相続したアパートより売却のハードルが高くなります。
アパート売却前の確認事項
アパートを売却する前に以下の3つのポイントを確認しておきましょう。
- ローン残高
- 家賃滞納者の有無
- アパートの所有期間
事前に確認しておくことで売却時期を見定め、より利益がでやすい売却方法を選べるようになります。
ローン残高
まずはローンの残高を確認しましょう。所有するアパートにローンが残っている場合、アパート売却による利益から返済する必要があります。
アパートの売却金でローンを返済しきれない場合は自己資金で足りない費用をまかなうため、全体的な収支をみるとマイナスになる可能性があることに注意しましょう。
家賃滞納者の有無
もし、家賃を滞納している入居者がいる場合は、アパート売却前にいち早く解決しましょう。アパートを購入する相手は、投資用の利回りの良い物件を探しており、収益性を求めています。
たとえば10戸ある部屋が現状満室だったとしても、その内の1戸が3ヶ月家賃を滞納しているとなれば、買い手は似たスペックで滞納のない物件を購入するからです。
悪質な滞納者がいる場合などは、管理会社と相談しながら具体的な対策を取り、家賃滞納者がいない状態を作りましょう。
アパートの所有期間
アパートや戸建てなどの不動産の売却を行い、売却利益(譲渡所得)が発生した場合に譲渡所得税が発生します。
売却利益(譲渡所得)とは不動産の売却代金から取得費(購入金額などの原価)および、売却する際に支払った譲渡費用(仲介手数料など)を控除した金額のことです。
売却利益(譲渡所得)に税率をかけて算出するのが譲渡所得税です。譲渡所得税は不動産の所有期間により「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」に区分され、それぞれ税率が異なります。アパートを売却する前に所有期間の確認を行いましょう。
譲渡した年の1月1日現在で不動産の所有期間が5年以下の場合、譲渡所得は「短期譲渡所得」に区分され、税率は39.63%(所得税30.63%、住民税9%)です。
一方、譲渡した年の1月1日現在で不動産の所有期間が5年を超える場合、譲渡所得は「長期譲渡所得」に区分され、税率は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)となります。
所有期間が5年以下の場合、所有期間5年以上の場合に比べると約2倍の所得税額になるところに注意が必要です。
アパート売却の流れ
アパートを売却するときの流れは、通常の不動産と変わりません。ただし入居者がいるため、賃貸借契約の引き継ぎやオーナー変更通知などの手続きが加わります。
- 不動産会社へ相談・査定を依頼する
- 不動産会社と契約を結ぶ
- 売却活動を開始する
- 売買契約・引き渡しをする
- オーナーの変更を通知する
1.不動産会社へ相談・査定を依頼する
まずはアパートの売却が得意な不動産会社を選び、数社に査定依頼しましょう。収益物件は査定が難しく、査定価格にバラつきが出る傾向にあります。必ず査定の根拠を説明してもらい、担当者の対応力などを総合的に判断しましょう。
2.不動産会社との契約を結ぶ
不動産会社が提示する条件や売却計画に合意できたら、売却を依頼する不動産会社と契約を結びます。
契約形態は「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」と、大きく分けて3種類です。一般媒介契約以外は他業者への同時依頼ができない契約ですが、その分担当する不動産会社は積極的に営業を行ってくれるメリットがあります。
物件価格や売却の時期などによって最適な契約形態は変わるため、不動産会社のアドバイスを受けて慎重に選ぶようにしましょう。
3.売却活動を開始する
売却計画にそって不動産会社とともに売却活動をはじめます。不動産会社がサイトに物件を登録し、住宅情報誌やWeb上に広告を出すなどの販売活動を行い、売主は問い合わせへの回答や内見依頼に対応します。
買い手から「購入申し込み書」や「買付け依頼書」が届いたら、交渉により売買の条件を調整します。
もし、アパートの収益性やエリアに大きな問題がないにも関わらず3ヶ月以上買付が入らない場合は、「相場に合った価格設定が出来ていない」もしくは「依頼した不動産会社の販売力が弱い」という可能性もあります。
価格の見直しや不動産会社の変更も視野に入れて検討すると良いでしょう。
4.売買契約・引き渡しをする
買い手との条件がまとまったら売買契約を結び、譲渡の準備をしていきます。売買契約時は、不動産売買契約書や重要事項説明書をはじめ、必要な書類を持ち寄って買主・売主・不動産会社の3者で売買契約を行います。
契約手続き完了後、引き渡し日が確定したらアパートに設定されている抵当権の抹消登記を行い、アパートの鍵や賃貸借契約書など各書類の引き渡しを行います。
5.オーナーの変更を通知する
基本的にはアパートの管理会社が対応するものです。念のため、オーナーの変更通知がされているかどうかしっかり確認しましょう。
新しい賃料の振込先などが早めに通知されていないと、売却後も家賃が振り込まれてしまい、新しいオーナーへの振込手続きなどの手間が必要になります。
アパート売却にかかる費用の例
アパートを売却する際は、譲渡費用として多くの費用が発生します。費用は売却前から算定できるものと、そうでないものがあり、正しい認識を持っていないと後の資金計画が狂ってしまう可能性があります。
アパートを売却する際、譲渡費用としてかかる費用は以下のとおりです。
- 測量費
- 仲介手数料
- 印紙税
- 抵当権抹消登記にかかる費用
- 譲渡所得税
- 消費税
測量費
不動産売買において、隣地との敷地境界がどこにあるのかは大切な確認事項のひとつです。
・売買契約後に登記面積と実際の面積に差があることが判明した
・隣地の建築物などが自分の土地に越境していた
など、売却後のトラブルを防ぐため、境界を明確にしておく必要があるからです。
測量には「現況測量」という大まかに土地の元用を把握する方法と、「確定測量」といって、隣接土地の所有者の立ち合いのもと、境界地点の確認・合意したうえで、土地の形状や面積を確定する方法があります。
どのような測量図が必要となるかはケースによって異なるため、不動産会社と相談のうえ、最適な測量図を準備しましょう。
測量費用は、現況測量で約10万から20万程度、確定測量は隣接土地所有者の数などでも費用は変わり、30万円程度かそれ以上になる場合が多いです。
仲介手数料
買主との売買契約が締結されたタイミングで、不動産会社への仲介手数料が発生します。仲介手数料は、宅地建物取引業法により上限金額が定められているため、不当に高額な仲介手数料が請求されることはありません。
成約価格が400万円を超える取引においては、成約価格×3%+ 6万円+消費税で仲介手数料の上限金額を算定できます。
印紙税
不動産売買契約書の作成に必要なのが印紙です。印紙税額は200円から60万円までと、不動産の成約価格によって変動します。不動産売買契約書1通につき1枚の印紙が必要となるため、必要な金額を確認しておきましょう。
参照元:国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」
抵当権抹消登記にかかる費用
アパートを購入した際に住宅ローンを利用し、アパートに抵当権を設定していた場合、抵当権を外すための登記費用がかかります。
抵当権抹消登記にかかる費用は、不動産の数×1,000円(登録免許税)です。通常、アパートは土地と不動産それぞれに抵当権が設定されているため、登録免許税は2,000円から5,000円程度かかるとみていいでしょう。
譲渡所得税・住民税
アパート売却前の確認事項でお伝えしたように、不動産売却後に利益を得た場合は譲渡所得税が発生します。
譲渡所得税には、所得税と住民税が含まれており、前述の所得区分(短期譲渡所得、長期譲渡所得)に応じた税率を用いて以下のように算定できます。
短期譲渡所得(譲渡した年の1月1日現在で不動産の所有期間が5年以下の場合)の税率は39.63%(所得税30.63%、住民税9%)です。
長期譲渡所得(譲渡した年の1月1日現在で不動産の所有期間が5年を超える場合)の税率は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)となります。
たとえば、6,000万円で取得した不動産が8,000万円で売れ、その際にかかった譲渡費用が500万円だと仮定した場合で計算してみます。
※簡略的な計算としているため建物の減価償却を加味しておりません
8,000万円-(6,000万円+500万円)=1,500万円(譲渡所得)
|
譲渡所得税率 |
譲渡所得税 |
|
|
長期譲渡所得 |
20.315% |
304万円 |
|
短期譲渡所得 |
39.63% |
594万円 |
このように、アパートを売却した後にかかる譲渡所得税の金額は、所有期間によって大きく異なる点に注意が必要です。
消費税
不動産の売買では、土地に対しては消費税は発生しません。建物部分にのみ消費税がかかります。しかし、売主が「消費税納付義務を持つ課税事業者」に区分されない場合は、建物部分も消費税を納める義務はありません。
消費税納付義務を持つ課税事業者とは、「アパートを売却した年の前々年度の課税売上高が1,000万円を超えている方」もしくは「前年の1月1日から6月30日における課税売上高が1,000万円を超えている方」のことです。
そのため、他に事業を行っておらず、はじめてアパートの売却を行うといった場合であれば、建物に対する消費税はかかりません。
反対に、前年または前々年に他事業などで1,000万円以上の所得がある方は、自分が消費税納付義務を持つ課税事業者に該当しないか確認する必要があります。
アパート売却のタイミング
築20年以内を目安にする
アパート売却のタイミングでとても重要なポイントのひとつが築年数で、築年数20年以内のアパートは比較的高く売却できるといわれています。
アパートは通常、築年数が経つごとに価値が下がります。建物自体が傷むことや設備等の劣化、外観が古くなるため、買い手を見つけるのが難しくなってくるからです。
また、減価償却の面からみても売却は築20年以内をおすすめします。減価償却費を計上できる期間は22年です。これは、アパートの多くが木造であり、木造の法定耐用年数が22年と定められているからです。
減価償却できる期間を過ぎてしまうと課税額が増えて不利になるため、このタイミングで売却を検討するとよいでしょう。
デットクロスを迎えた(減価償却を終えた)とき
経費に計上できる減価償却は、アパート経営において重要な要素です。減価償却は帳簿上の支出であるため、減価償却がある期間はキャッシュフローに余裕ができます。減価償却期間の終了と同時にデットクロスを迎える可能性もあるため、売却を検討するべきでしょう。
デットクロスとは、ローンの元金返済が減価償却費を上回る状態を指します。金融機関からの融資を受けてアパートを購入した際、経費に計上できる減価償却の期間が終わると、元利均等返済の“経費になる利息の返済分”より、“経費にならない元金の返済分”が増えます。
そのため、経費計上額が減るなどして税金が増え、キャッシュフローがマイナスになってしまうのです。
空室がないとき
投資用アパートの購入層は、投資家に限られます。投資家の立場としては、空室が多いアパートよりは満室状態でオーナーチェンジできるアパートの方が当然魅力的です。
入居者の退去は予測できないため、現在満室である場合は築年数による経年劣化、減価償却時期なども含めて、売却の時期として検討しましょう。
アパートを高く売却するためには
アパートを高く売却するには適切なタイミングを見極め、アパートの市場価値を最大化することが重要です。売却に最適なタイミングは前述の通りですが、ここからはアパートを高く売却するために行うべき市場価値の高め方を解説します。
空室率を下げる
売却のタイミングのところで前述したように、アパートは満室である方が売却できる確率が高まります。また、条件がよくなれば売却額を上げられる可能性が出てきます。
空室率を下げるために、即入居可能な備え付けの家電や家具を用意する、リフォームするなど、さまざまな対策を講じましょう。
家賃の水準を保つ
さまざまな対策をしても空室が埋まらない場合、家賃を下げて入居者を募集しがちですが、できるだけ家賃は下げずに入居率を上げましょう。一棟アパートの売却は利回りが大きく影響します。年間で家賃収入が減るとそれだけ売却価格も下げる必要が出てくるのです。
空室を埋めるにはいくつか方法がありますが、家賃を下げないようにするには、客付けが得意な管理会社へ変更したり、1カ月のフリーレント期間を設けたり、室内をリフォームするなどの対策を講じましょう。
滞納問題を解決する
アパート売却を検討している場合、滞納問題は真っ先に解決するべき問題です。単純な振込の遅れなどであれば、電話や口頭での注意喚起、それでも遅れるなら催告状などの文章を送るなどの流れになります。
ただし悪質な滞納者に対しては管理会社と相談しながら、滞納している入居者とその連帯保証人に内容証明郵便を送るなど、具体的な対応が必要になってきます。
場合によっては法的措置をとって強制退去という手段も必要になります。悪質な滞納者に対しては、1日も早く対応することが重要です。
まとめ|アパートの売却について迷ったら、まずは不動産の専門家に相談を
アパート経営を続けるべきか、売却を行うべきかについては、現在の住宅ローン残高や毎月の家賃収入、アパートを所有している期間などさまざまな観点から判断する必要があります。
所有するアパートについて、「このまま維持するより売却したほうがいいかも」と感じたときは、まず現在のアパートの価値や相場を正しく知るために専門家の意見を聞いてみましょう。価値を正しく知ることで、今後の具体的な計画を立てられるでしょう。
「アパート売却について詳しく知りたい」という方は、ぜひ当社にご連絡ください。当社は新潟市を拠点に不動産売却エージェントとして、不動産の売却・購入を一括サポートしています。お気軽にご相談ください。
▼物件売却のお問い合わせはこちら
https://furusatofudousan.com/takehana/contact_assessment/
▼物件購入のお問い合わせはこちら